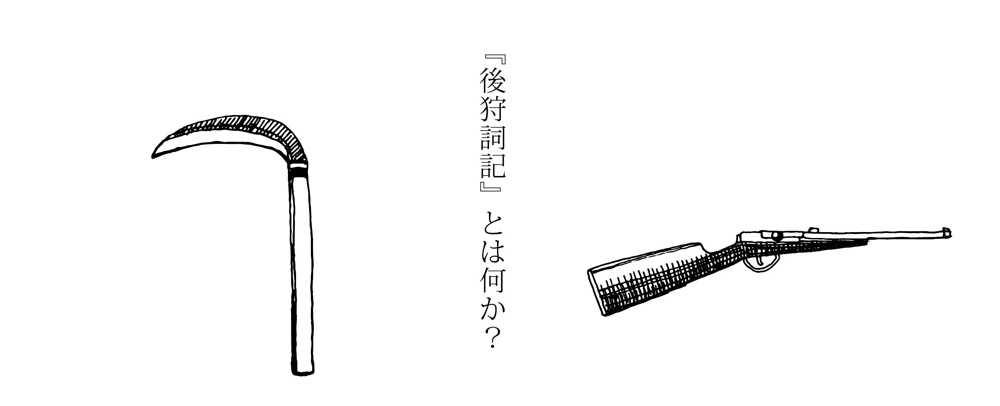
『後狩詞記』とは何か?
大河内の椎葉徳蔵宅で見た『狩之巻』と第した文書は、山の神に関する秘密の伝書である。それを出版して公開してしまう事に、神の祟りを恐れる人もいるかもしれない。しかし、柳田はこう言い切っている。「もはや山の神の言い伝えは昔のことで、今は、ほとんど役に立っていない」と。
「ちょっと言い過ぎではないか?」と一瞬僕は思った。しかし、良く考えてみると時代は既に明治末である。汽車も写真も常識の、文明の時代なのだ。いかに山の中の村とはいえ、山の神の言い伝えや畏れが薄れていたのも当然だ。
『後狩』という言葉は、「鉄砲の時代の狩り」という意味である。弓矢で獲物を追っていた時代の「狩り」に対して使った言葉である。 柳田が『後狩詞記』で残したかったのは、むしろ新しい文明の時代になっても、猟師たちの間で使われている「生きた言葉」であった。
日本全国で猪が減り、狩りが廃れていく中、山の中の地形を細かく言い表す言葉を採集、残したいというのが柳田の望みであり、それは冒頭に紹介した手紙で中瀬村長へ懇願したことでもあった。
そして、中瀬村長はその願いに応えて、椎葉で使われている狩りに関する「ことば」を解説と共に柳田に書き送った。それは次のように分類されて『後狩詞記』の主要な部分となっている。
「狩り場の名称」
「狩りことば」
「狩りの作法」
「いろいろの口伝」
その中には、例えば「ニタ」=(猪が地面に窪みを作って湿地とし、水を飲んだり体に泥を塗りつけるのに用いる場所)や「ウジ」=(猪の通り道)など、猪の習性に関するものももちろん多い。
「セイミ」=少し水が沸いている場所。
「シクレ」=棘のある草木の茂みで、猪が逃げ込みそうな場所。
「モッコク」=シクレの中で最も通りにくい場所。
「ヤゼハラ」=シクレの広くある場所。
「ドサレ」=砂や小石が多い急傾斜で、猪も逃げるのに苦労するので、鉄砲で狙いやすい場所。
などなどなど・・・。例えば、これは僕も村の人たちから直接教えられたことがある「カマデ」と「カマサキ」。鎌を使う時に手のある方向、つまり(右利き限定だけど)右が「カマデ」。刃の先がある方向、つまり左が「カマサキ」。
この他にも焼畑に関係して、草木の育ち方の微妙な状況の違いを言い分けた言葉や、「サエ」=(村から離れた山の方)や「コウマ」=(サエとは反対に村里のある場所)など、地形や場所を細かく表す言葉が多く紹介されている。その数、狩場の名称だけでも実に四十一。
都会に暮らす人たちには単に「山」とか「谷」とか「麓」にすぎない地形の中に、それだけたくさんの意味を持った場所が存在すること。それを柳田國男は文化的な、また精神的な「豊かさ」と考えていたのだろう。
『後狩詞記』によって日本民俗学の扉を開いた柳田國男だが、一つ見誤ったことがある。それは、冒頭に紹介した中瀬村長への手紙の中の一文。
「御地方と雖、猪ハ段々少なくなり、猪狩の慣習も将来漸く衰え候事他地方の山村と同しからんと想像せられ候」
確かに一時は猪も減り、猟師の数も減ったとは言えたが、大正、昭和、平成の時代を過ぎ、令和の現在に至っても椎葉の猪狩りは健在だ。柳田先生、令和の椎葉に乗用車で広くなった道路を通って訪れたらどう思うだろう。
「ちょっと言い過ぎましたかな。失敬失敬」と脱帽するに違いない。

令和の時代の椎葉の猟に同行させてもらう。『後狩詞記』の「後狩」とは先述した通り鉄砲を用いた狩りという意味だから、柳田が目にした猟と、今の猟の様子が大きく変わっているということはないだろう。
猟師は軽トラに犬たちを乗せて猟場に向かう。犬の首にはGPSが装着されている。その辺りの様子は確かに百年の時の流れを証明するものではあろうが、相手は野生の猪である。そして彼らが棲むのは山の奥の方「サエ」であり、潜むのは棘のある草木が生い茂った「シクレ」だ。「ニタ」で泥を体に塗りつけ、「ウジ」を通って移動するのだ。
荷台のケージから飛び出した犬たちは迷わず林に分け入り猪を探す。猪は柴を集めた寝床「カモ」で息を潜める。猟師は犬を信じ、落ち着いて山を登っていく。
やがて犬の吠え声がけたたましくなり、一発の銃声が山にこだまし、空に吸われてまた静寂が訪れる。犬と人と猪の命の預け合いは百年前も今も同じことなのだ。


何度か猪の解体も見たことがある。猟や解体の現場で『後狩詞記』に記された作法がそのまま行われている訳ではもちろんない。その事は、柳田國男自身も当時から予見していた。それどころか、彼はおそらく一一四年経った今もここ椎葉で、猪狩が盛んに行われているとは予想できなかったのではないかと思う。
文明がめざましい勢いで発達していた明治末、椎葉もやがて開発の波にのまれて、猪もいなくなり、狩も途絶えてしまうだろうと思っていたはずである。だからこそ、「その前に」と『後狩詞記』を世に残したのだ。
その点では、この地域の山の深さ、豊かさ、そして狩りにしても、採蜜にしても、焼畑にしても、それを大切なものとして続けていこうとする人々の思いが、東京に暮らす柳田國男の想像を超えていたと言えるのではないだろうか。
猪の解体を見る度に意外に思うこと。それは猪の首、その不思議なほど穏やかな表情だ。だから僕は思う。猪は命を失ったのではない。山の神から預かった命を肉を通して人間に預けたにすぎない。人もいずれ命を返す。来年には猪の赤ちゃん瓜坊が新しい命を宿して山を駆け回る。その営みは柳田が中瀬村長らと語り合ったあの日と少しも変わっていないのだと。


椎葉滞在四日目、柳田一行は不土野の庄屋、那須源蔵邸に宿泊する。初日に宿泊した下松尾の松岡久次郎に並ぶほどの名家で、酒造業も営んでいた。
椎葉型の立派な屋敷は屋根が茅葺きから瓦葺きになった事以外は、柳田が宿泊した頃の姿をほぼ留めている。
豪奢な日本画が描かれた襖や屏風、緻密な組み木細工の施された欄間。蔵や天井の上の部屋に保管されていたというさまざまの文書や調度品は、この家ばかりかこの地域の豊かさを物語るもの。そしてその文化度の高さにも驚かされる。宮崎、日向、延岡との交流ばかりではなく、交易の多くは駄賃付け道を通じて、熊本県側と行われていた。「椎葉は宮崎県の山の中」という概念は全く当たらない。それは俯瞰してみれば分かる。九州脊梁山地という視点で見れば、ここは宮崎県の最前線とも言えるのだ。




那須源蔵のひ孫、当代の鉄郎さんは今も柳田が宿泊したこの家に暮らしている。母の綾子さんは上椎葉の施設にいるが、数年前僕が訪れた時にこんな話をしてくれた。
「この屏風見てください。役者や花魁のような人物が描かれているでしょう。小さい頃、薄暗い部屋でその目が怖くて怖くて・・姉妹たちとつい、その目をガジガジっと、引っ掻いてしまってね。」
源蔵さんも次の代の安蔵さんも男子が生まれず養子を迎えた。安蔵さんの娘、綾子さんと婿養子に迎えた政登さんの間に生まれた鉄郎さんは自分の事をこう評して笑った。「那須家におよそ百八十年ぶりに生まれた男子でね、婆さんたちに甘やかされて育ったもので、僕は根性がないわ。」
いやいや決してそんな事はない。柳田たちが語り合ったであろう囲炉裏のある部屋に正座した姿は、この名家を引き継いだ誇りと、次の世代に引き継いでいくという信念の強さがにじみ出ているようだった。

